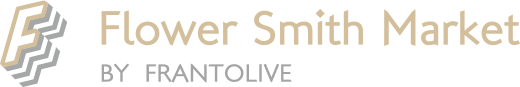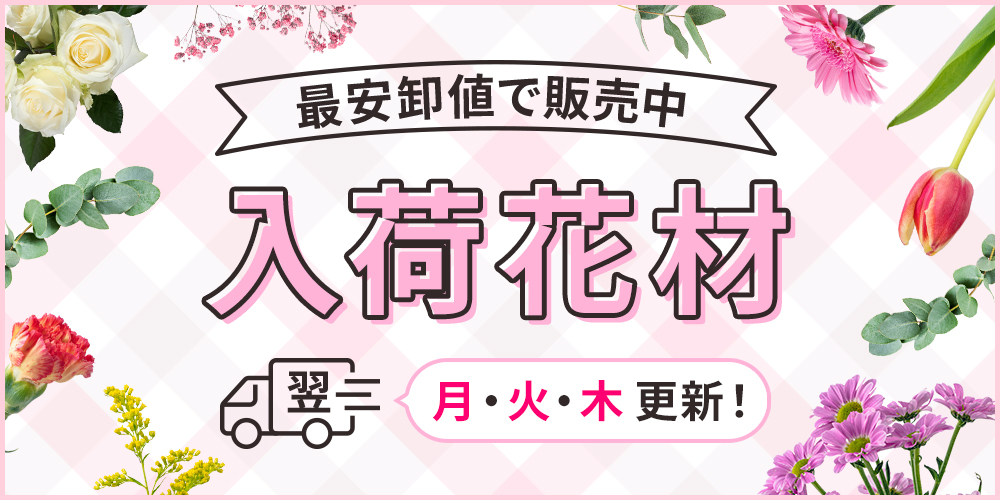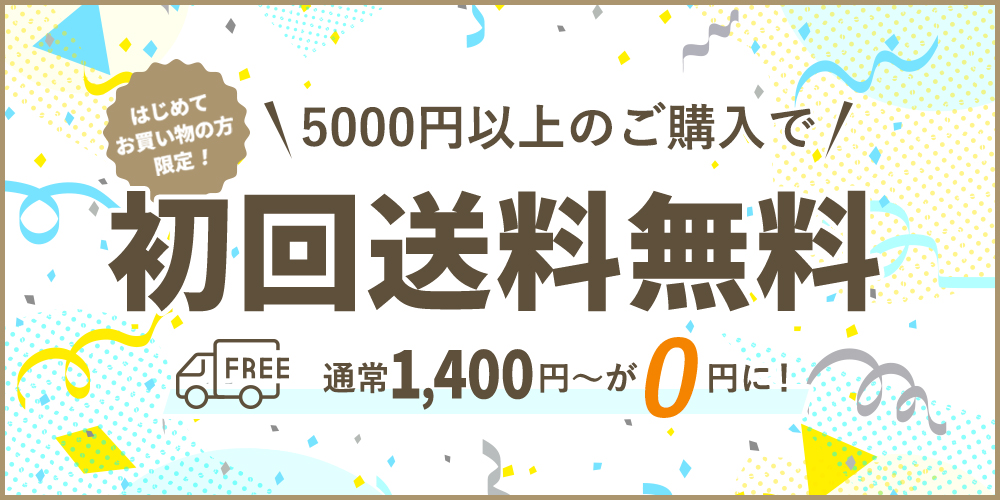花屋は開業までのハードルがそこまで高くないので、、初心者でも比較的開業しやすい業種です。
しかし、利益を出して経営を安定させるのは難しく、実際のところ多くの花屋が早い段階で開業に追い込まれてしまっています。
ここでは、花屋の経営が難しいとされる理由とその対策法についてご紹介します。
生花の品質管理が難しい
花屋経営が難しい理由として大きなものとして、生花の品質管理の難しさがあります。
花は日持ちが短い商品なので、温度と湿度の管理や、毎日の手入れが適切でないと鮮度を保つことができません。
また適切な管理をしても日数が経てば駄目になってしまうため、仕入れをしたら早い段階で売り切る必要があります。
売れ残ってしまった生花は廃棄せざるを得なくなり、この廃棄量(ロス)が多いと、仕入れコストだけがかかり利益が上がらない原因になります。
対策
仕入れた生花の廃棄を減らすための対策方法は以下のとおりです。
- フラワーキーパーを活用して、鮮度を長く保てる工夫をする
- 小ロットずつ多種類の花を仕入れる
- 花ごとの売れ行きが見えてきたら、大ロットで仕入れる花、小ロットで仕入れる花を選別していく
花の品質管理を簡単にしたいなら、フラワーキーパーを導入するのがおすすめです。
フラワーキーパーとは、切り花を入れておけるガラスケース型の冷蔵庫のことで、フラワーキーパーの中に生花を入れておくことで鮮度が落ちるスピードを緩やかにしてくれます。
またロスを減らすためには、「売れる量だけを仕入れる」ことが重要です。
特に開業したばかりの頃は、品数を多く見せるために数多くの花を店内に並べたくなり、たくさん仕入れがちになってしまいます。
客層や売れ筋が読めないうちは、いろいろな花を少しずつ仕入れることで、ロスを減らすことができます。
来客数や売上が伸びてくると、花ごとの売れ行きも見えてくるので、その都度仕入れる花や数を調整していきましょう。
季節による売上の変動が大きい
花屋の繁忙期は、卒業・入学シーズンの春、母の日前、お盆、クリスマス・お正月シーズンなどがメインで、年間を通して日数はそれほど多くありません。
繁忙シーズン以外に売上を伸ばす工夫が難しいため、繁忙期以外の季節はどうしても売上が落ちてしまいます。
その他のシーズンに売るためには、父の日、敬老の日、ハロウィン、バレンタインといった月ごとのイベントを活用する必要があります。
対策
季節による売上の変動を少なくするための対策法としては、以下のようなものがあります。
- 季節のイベントと需要を把握する
- イベントに合ったPOPを作るなどのプロモーションをする
花屋は季節によって売上が大きく変わってしまうため、季節のイベントは逃がせません。
イベントごとに品種の需要も異なるので、イベントに合わせた花を仕入れることも重要です。
お盆に使う花の需要が高まる7月~8月は、菊や白いユリなどお供え用の花をメイン商品にする、秋はハロウィン用のアレンジメントを作る、クリスマス時期は赤い花を多めに仕入れるなど、常に季節を意識した店づくりが成功する秘訣です。
また繁忙期であってもアピールができていないと売上を上げるのは難しいので、イベントに合ったPOPを作るなどのプロモーションも行いましょう。
利益を出すためのノウハウがない
花屋に限らずお店を経営するためには、利益を出すためのノウハウを活用して、戦略を立てたうえで経営していくことが利益を伸ばすコツです。
しかし花屋は、花を取り扱うプロとして花の種類やそれぞれの花に合った管理方法、フラワーアレンジメント、仕入れの仕方などと、覚えることが非常に多くあります。
花屋に必要な知識を覚えることばかり必死になると、経営について勉強する時間を取ることは難しくなります。
経営について勉強できないことで、利益を出すための戦略が十分にできないと、赤字が続いて最悪の場合廃業に陥ってしまうリスクが高まります。
対策
経営に関する勉強をする時間がないという方も、簡単なことからならすぐにでも始められます。
利益を出すためにすぐにでも取り掛かれる対策は、以下のとおりです。
- インターネット仕入れを利用し、仕入れにかかるコストや時間を削減する
- 小ロットを低価格で仕入れられるサービスを見つける
- SNSを活用してマーケティングを強化する
花屋の仕入れ方法には、市場や卸業者を利用する方法がありますが、コストや時間を削減したいならインターネットで仕入れるのがおすすめです。
インターネットであれば、営業時間などを気にすることなく注文でき、お店まで直接届けてくれるので、結果として人件費削減にもつながります。
さらに利益を出すためには、マーケティングを強化して集客に力を入れる必要もあります。
集客する方法はさまざまありますが、無料かつ拡散力の高いSNSを活用するのがおすすめです。
SNSを活用した集客方法などは、後ほど詳しく解説します。
小ロットで仕入れできるサービスを活用
コストを削減するためにも、多種類の花を小ロットで仕入れでき、単価の低い仕入れサイトを見つけることが重要です。
当店「フラワースミスマーケット」では、700種類以上の生花を取り扱っています。5本~の小ロット、卸売価格で購入できるため、コストを削減したい小規模のお花屋さんにぴったりのサービスです。
フラワースミスマーケットの特徴はこちら