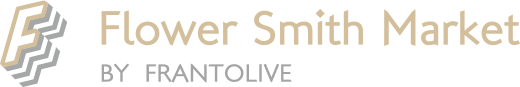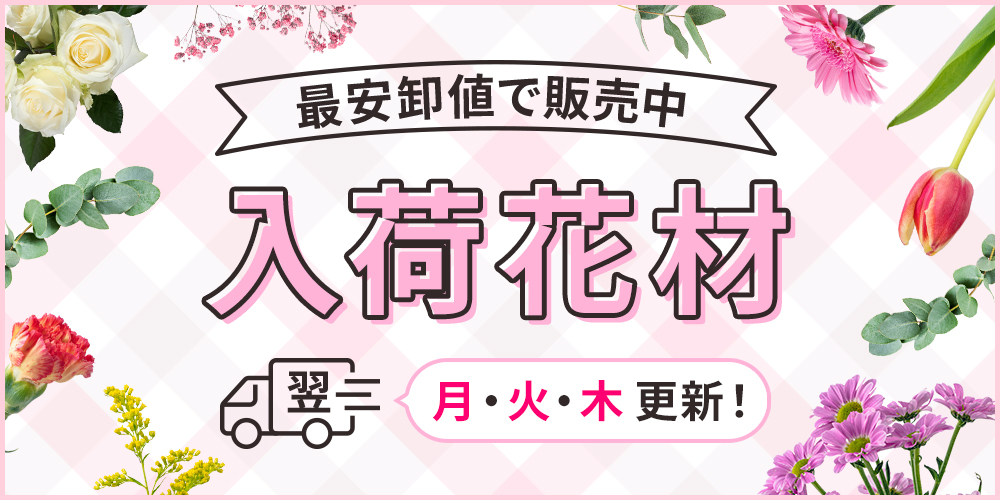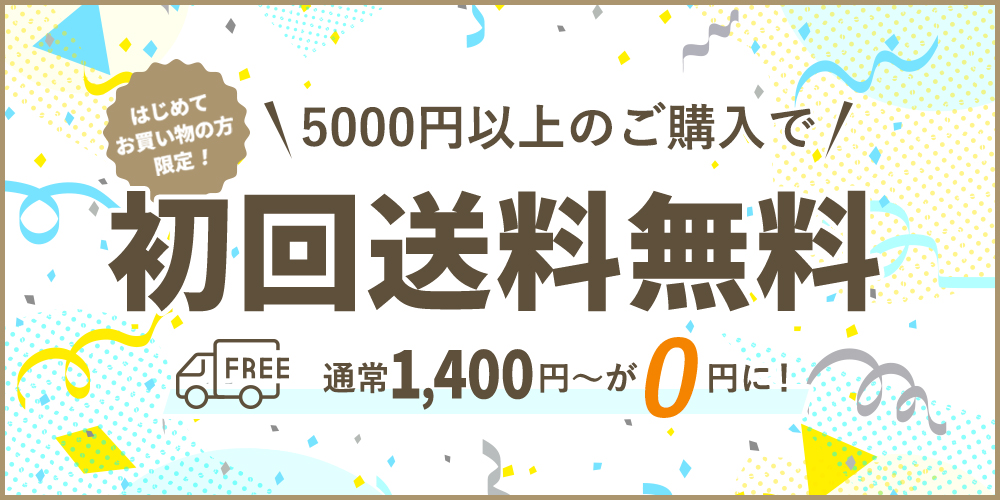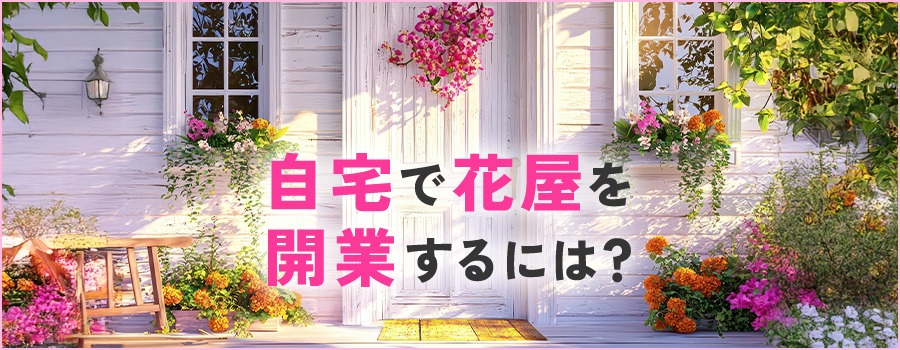- 花が好きなので自宅で花屋を開きたい
- 自宅を店舗にすることで家事・育児と仕事を両立したい
- 物件を借りる場合と自宅を利用する場合、何が違うのかを知りたい
花屋は特別な資格がいらず比較的狭いスペースでもお店が開けるため、自宅で開業する方も増えています。
現在、自宅で花屋の開業を考えている方の中には「花が好きなので自宅で趣味を活かしたお店を開きたい」という方のほか、「自宅でお店を開くことで家事・育児と仕事を両立させたい」という主婦の方も多いのではないかと思います。
その一方で自宅で花屋を開くには、店舗を借りるより綿密な営業戦略や近隣住民への配慮なども必要となります。
この記事では、自宅で花屋を開業する場合のメリット・デメリットのほか、開業までの準備、集客するためのコツやトラブルを起こさないための注意点を解説します。